どうもマツローです!
プロ野球選手会が2019年3月よりNPBに導入を提案していた「現役ドラフト」(仮称ではブレークスルードラフト)が、現実化に向けて動き出しています。
2020年1月22日にプロ野球実行委員会による制度案が提示され、12球団の方針が大筋合意したことが明らかになりました。
今後、この制度案に選手会が合意すれば、3月のプロ野球実行委員会で本年度からの導入が決定します。
では「現役ドラフト」とは具体的にどのような制度なのでしょうか?
この記事では現役ドラフトの目的や意義を解説。現時点で考えられる、現役ドラフトのメリットやデメリットと共にご紹介します。
スポンサーリンク
Contents
現役ドラフトとは?

現役ドラフトとは、「出場機会に恵まれない中堅選手に新たな環境でチャンスを与える」ことを目的とし、これまでチーム事情などで出場機会が得られなかった選手の活性化を狙った制度です。
制度案は、MLBで毎年12月に行われている「ルール5ドラフト」を参考に考案されています。
ルール5ドラフトは、チーム事情によりメジャーリーグに昇格できない選手の救済措置として設けられた制度で、基本的にメジャーリーグ40人枠に登録されていない選手が対象となります。
在籍年数により対象となる選手が異なっていたり、ルール5ドラフトで指名した選手の一軍登録にも決まりがあったりと、安易な選手の引き抜きを防ぎ、かつ飼い殺しも防止できる制度となっています。
ミネソタ・ツインズで開花したヨハン・サンタナ選手や、シンシナティ・レッズで復活したジョシュ・ハミルトン選手など、多くの成功例がみられており、日本では中日ドラゴンズなどで活躍したエクトル・ルナ選手やトニ・ブランコ選手が、ルール5ドラフトを経験しています。
しかしMLBとNPBではリーグの規模が違いますので、ルール5ドラフトをそのまま適応することは難しいでしょう。そのためNPBにあわせ、新たに考案されたのが現役ドラフトです。
では、現時点でまとめられている現役ドラフトのルールをご紹介します。
実施時期は7月20日前後
今季のプロ野球は東京オリンピック開催により、7月19日~8月13日まで中断となり、7月19日・20日はオールスター戦が開催されます。現役ドラフトはこの時期に実施される見通しです。
指名対象として各球団8名の支配下登録選手の名簿を提出
各球団で支配下登録選手の中から8名の選手の名簿を提出します。
なお現役ドラフト実施までにトレードを行った球団は、他球団へ移籍した人数を8名から差し引くことができます。ただし3名以上のトレードを行った場合でも、最低6名の支配下登録選手を名簿に記載しなくてはなりません。
各球団、最低1名を指名する
名簿に記載されたが指名されなかった選手については、非公開とします。なお、指名された選手の拒否権はありません。
ちなみに現役ドラフトの対象除外となる選手についての詳細は、正式に明らかにされていません。以下の条件に該当する選手は除外となる見通しです。
- 前年のドラフト会議で指名された新人選手
- 前年11月から7月10日までの移籍選手
- 外国人選手
- 育成選手
- 複数年契約の選手
- 一定の高額年俸の選手
- FA有資格者
このように、MLBのルール5ドラフトとNPBの現役ドラフトでは、現時点でも既に大きく違う点が見受けられます。
では、現時点で考えられる現役ドラフトの問題点、メリット・デメリットを挙げてみます。
現役ドラフトのメリット
まず、出場機会に恵まれない選手にとって、環境が変わることは大きなチャンスとなります。
例えばチームに捕手が8名在籍する場合、仮に一軍で捕手3人制を取っていても二軍には5名の捕手がいることになります。この状態では二軍の試合数を考えても、十分な試合経験が得られるとは考えにくいのではないでしょうか?
このような選手が捕手の人数が少ないチームへ移籍し、試合経験を積んで能力を開花させることができれば、新たなスター選手が生まれる可能性も増えます。
また、シーズン中に一軍・二軍を行き来する選手や、守備ポジションが主力選手とかぶっているため出場機会が得られない選手も、現役ドラフト候補者名簿に記載されれば、移籍先のチームで活躍する可能性があるのです。
現役ドラフトのデメリット【球団主導の候補者名簿】
現時点の制度案で一番問題視されているのが、「現役ドラフト候補者が球団主導で決められてしまう事」です。
球団としては主力選手の控えや将来有望な選手は、現時点でレギュラーではなくてもチームにとって必要な選手です。
そして同リーグ他球団へ移籍した有力選手が足りないポジションを埋め、自チームの脅威になっても困るのです。それならば他リーグの有力選手とトレードし、自チームの足りないポジションを埋めるほうが得策と考えるでしょう。
このことをふまえると現役ドラフト候補者名簿に記載される8名は、出場機会が得られない有力選手というよりは「シーズンオフに戦力外通告をされる可能性のある8名」であることが予想されます。
この制度案については早くも「不要な選手の押し付け合いになるのではないか」という声も上がっています。
現役ドラフトのデメリット【実施時期】
他に問題点としてあげられているのが「現役ドラフト実施時期」です。
2020年は7月20日前後に行われる見通しですが、シーズン中の移籍ともなればサインプレーの変更が必要となります。2020年は東京オリンピックでシーズンが中断されるため、試合がない期間にサインプレーの変更をする事は可能です。
しかし通常のシーズンですと、この時期にサインプレーの変更をし、後半戦に臨むのは難しいのではないでしょうか?
特に優勝争いをしているチームにとってシーズン後半のサインプレー変更は、試合に集中したい選手に良い影響を与えるとは思えません。
現役ドラフトのデメリット【情報漏洩の可能性】
最後に懸念されるのが「現役ドラフト候補者名簿の漏洩」です。
実はNPBでも過去に移籍の活性化を図り、1970年に「トレード会議」、1990年に「セレクション会議」といった制度が導入されたことがありました。
このセレクション会議の後、他球団の名簿に載った選手を別の球団の監督が記者に漏らし、騒動に発展したことがあったのです。
FAのプロテクトリストも非公開とされていながら、関係者を通じて漏れてしまっているケースが毎年のようにみられます。
もし同様に現役ドラフト候補者名簿に載った選手が漏れてしまったら、チームの士気にも影響するのではないでしょうか?
現役ドラフトの主役はあくまでも選手
近年導入されたコリジョンルールやクライマックスシリーズ・交流戦、DH制の導入など、これまで新たな制度がNPBに導入される際、メリットよりもデメリットの方が多く取り沙汰されてきました。
しかしこれら制度も、選手会やプロ野球関係者・プロ野球ファンの厳しい目があり、より良いルールに見直されて昨今のNPBを盛り上げるひとつの要因になっています。
現役ドラフトも本来の趣旨は、なかなか一軍に定着できない有力選手が必要とする球団に活躍の場を求め、チームの活性化を促す制度であったはず。
埋もれていた才能が開花する姿は、チームにも新天地のファンにも勇気と感動を与えます。その本来の目標を見失わず、ひとりでも多くの選手に光が当たる制度として機能することを願ってやみません。




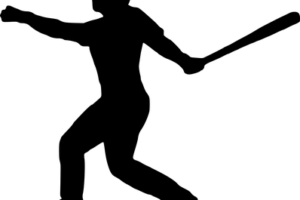


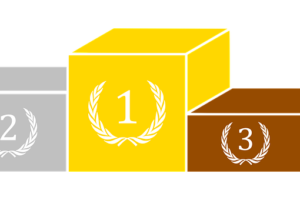





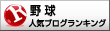
コメントを残す